海外工場現地法人で社長しています。
3年前(私の赴任前)にキャリア採用で雇ったマレーシア人の工場長が最近、強いリーダーシップを発揮し、元気になってきました
その背景について考えました
結論
「現場責任者が能力を発揮できる環境を整える」
ことが採用の大前提と言う話です
赴任直後の社内の状況
あくまで主観的ですが、
私が赴任したのが4か月前
その当時の社員の仕事ぶりにいろんな問題点を感じていました
工場の現場について話すると分かりやすいので、工場を中心に話しますが
・工場の最も基本の5Sができていない
・工程もしょっちゅう止まる
・生産性も上がらない
・生産計画を守れないので、お客様に迷惑をかける
・迷惑を減らすため、在庫をたくさん持つ
という、かなり厳しい状況でした
この現状を、3年間にキャリヤ採用した現地人の工場長と話しすると
「わかっているが、改善がなかなか進まない」
と非常に悩んでいるようでした
なぜななかな進まないのか理由を聞いても、歯切れが悪い
この工場長、話をしてる分には非常に優秀で、工場をどうするべきか熱い思い持っており、いろんな取り組みをしようと努力しているのを感じます
しかし、実行段階でその思いを現場に伝えられない、マネジメントできないもどかしさを感じているようでした
いったん社長も現場に入ってみよう
ということで、何が問題なのかわからないまま、私のいつもの方法ですが、自ら現場に入り生産状況の「見えるか」と「そのレビュー」を行うことから始めました
「見えるか」自体は進んでいる工場で
・生産計画台数と実績の差
・工程の稼働時間
・実際に発生したロス
など、すぐにデータは出てきて状況をつかむことはできました
ですので、それらの中にある問題点をひとつづつ解決することを指示しました
問題を関係者と共有し解決する活動は、私が赴任以前からしていましたが、どうもその内容が本質ではなく、生産に直結する問題でないことも多かったので、その点を指導することにしました
また5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)の活動も全くダメで、
・どこに部品があるのかわからない、
・現場の何を触っても埃で真っ黒(設備、部品箱)・
・組み立てラインの横には、必要でない部品含めたいろんなものの山積み
・ゴミがアツコチに落ちていても平気
かなり厳しい状態でした
これも、現場を定期的に巡視し、何ができていないか教えることから始め、必要な掃除道具を購入する予算を渡しました
4か月後
そして4か月経過
あるべき姿には程遠いですが、現場に「改善する文化」が芽生えてきたのを実感します
先の工場長も、非常に積極的になり活動が活発化してきているようです
発言もポジティブになってきました
ローカルのGMクラスも改善の姿勢に加え、私の発言から何かを学ぼうとする姿勢を感じることができ(全員ではありませんが)、私自身も非常に現場に行くのが楽しくなっています
変化の理由1
なぜこの変化を感じることができたのかを考察してみます
以前、「【改善活動が継続する文化の醸成】について考える」というタイトルで記事を上げました

この中で、
「トップの意思」 「教育」 「評価」
この3要素が改善を継続するには必要と書きました
今回の出来事はまさにこの「トップの意思」が現場に伝わったことが大きいかと思います
今までのトップも製造現場を変えていく方針を出していないわけではありません
ただ、この方針がどこまで伝わっていたかは、聞く限り疑問が残ります
別に、過去のトップを非難しているのではなく、トップとしての業務は多岐にわたり、現場に入っていくことは非常に難しい環境にであります
さらに、製造に詳しくないトップも多く、そのトップからすれば現場に入っていくことは相当ハードルが高くなります
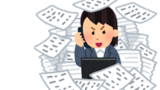
加えて、現場を強化するのは戦略を考えるよりはるかにエネルギーと時間が必要です
丁寧に継続的に会話し、一緒に取り組む必要があります
幸い、私は工場での経験が長く、かつ、現場を見るのが非常に楽しい性格で、その性格のおかげで現場の課長、班長達と直接会話することが多い
その結果、現場に対し社長の本気度を理解してもらうことができたと感じています
トップの意思って、書類に書いただけでは伝わらないことがよくわかりました
そういう意味では、私は不得意分野については、私の思いを現場に伝えることができていない可能性は高いと言えるでしょう
変化の理由2
変化の理由として、トップの意思を理解してもらえたことを上げましたが、それ以上にローカルの工場長の行動が変わったことが大きいと感じています
なぜ変わった
かれはキャリア採用として迎え入れられたのですが、その職場にはプロパー社員(もともと長く勤務している社員)がとても多くいます
そのうえ50歳代の工場長の年上社員が非常に多い
これらの社員は、長く「現場改善」などという活動を本気でした経験もなく、給料だけは高いけど日々当たり障りのないルーティン仕事に満足している人たちです
そういう社員たちに、外様の工場長が改善を訴えてもなかなか進まないという大きな問題に悩んでいたようです
そのような状況の中で、トップが現場に入り込んできたのは工場長を大いに勇気づけたようです
マレーシアという国はヒエラルキーが強く、国全体でいえば国王~役人~一般市民のヒエラルキーは非常に強く、役人に対する文句は一切言いません
日本とはえらい違いです
会社組織でも、社長の言うことはルールから離れてることでも従います
(これは、逆に社長はその発言・行動を非常に慎重にしなければならないことを意味します)
つまり、工場長としては、いままで指示していても従わないプロパー社員に対しても
「社長があそこまで言っている。社長からの強い指示」
と言えば、かなり動かしやすく、彼自身が強く指示できる環境になるということです
これは、工場長の能力の問題ではなく、職場・会社の環境の問題と考えています
キャリア採用で入った部門責任者が能力を発揮できる環境づくり
会社を成長させるためには非常に重要な要素と感じた経験でした
まとめ
私のつたない製造現場での経験を書かせてもらいました
キャリアで採用した部門責任者が実力を発揮しやすい環境作りの重要性を感じたので記事にしました
あくまで、環境ができていないこと問題と思って、私自身が動いたのではなく、たまたま、活動したことがいい方に向かったので、その理由を考察した結果です
また、前進を感じることができたのは、ベースに責任者自身がその意思、スキルを持っていることが前提になります
また、現場もスキルを持っているがその使い方がわからない、上司の理解がない(この場合、プロパーの幹部社員)もったいない状況の場合、環境を整えることで、現場が大きく成長することがあります
幸い、今回はそのベースがあったので、比較的短期間で進んだと考えています
これからどう変化していくのかを非常に楽しみにしています




コメント